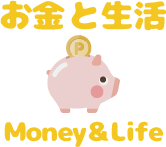- トップページ
- 墓じまいのトラブルや手順について
墓じまいのトラブルや手順について
墓じまいを行う際には、事前にしっかり計画を立てて行う必要があります。
何故なら、様々なトラブルに発展することがあるからです。
墓じまいで実際に起こるトラブルの例を始め、代行してもらうときや手順はどのようにするべきかを紹介します。
墓じまいのトラブル事例(裁判・後悔したこと等)

墓じまいでは実際に様々なトラブルが起きていますので、事前に確認しておきましょう。
菩提寺の僧侶から離檀料を請求される
墓じまいのトラブル例の中には、菩提寺の僧侶から離檀料を請求されるケースがあります。
菩提寺によっては、お寺を離れる際に掛かる離檀料をあらかじめ決めていることもあり、それを知らないときは問題になる可能性があるのです。
今までお世話になった菩提寺に何の相談もせず、勝手に墓じまいを行う手続きを進めているときに、後から高額の料金を請求されることもあり、それが原因でトラブルに発展します。
墓じまいをすることを菩提寺の僧侶に伝えたとしても、その際に数百万円の離檀料を請求された、というようなケースも実際に起きています。
この件に関してはお寺の性質上、檀家からのお布施や寄付金などが収入源になっているのが、大きく関係しています。
ただ近年の少子高齢化や核家族化、過疎化などの関係もあり、檀家制度自体が衰退し続けていて、お寺の経営が危機に立たされている点も大きく影響しているのです。
そもそも離檀料という言葉は仏教用語などではなく、近年墓じまいや改葬などの増加によって、メディアが独自に作った造語と言われています。
また檀家になるときは、「離檀する際に離檀料を支払う」などの契約を締結しない限り、必ずしも支払い義務が生ずるものではありません。
しかし実際に離檀料を請求されるというトラブルもあるようですので、これについては特に注意しておく必要があります。
石材店とのトラブル
墓じまいでは、石材店とのトラブルもよく起きています。
お墓が建っている土地というのは、菩提寺などからその土地を使用する権利を購入しているだけですので、土地そのものを利用者が購入しているとは限りません。
そのため土地を借りている場合は、墓じまいを行う際に墓石や解体をして撤去する必要があるのです。
そして墓地を更地にした後は、お寺に返還する必要があります。
こうした墓石の解体や撤去工事は石材店が行うのが一般的であり、その際には菩提寺が提携している石材店でなければ工事して貰えない、というケースがあるのです。
そして解体や撤去を行う際に、予想外の高額な費用を請求されることがあります。
一般的にお墓を撤去して整地にする際には、1平方メートルあたり10~20万円が相場と言われています。
そのためお墓を撤去する際には、相場を参考にして判断すると良いでしょう。
ただお墓が山中にあるなど、重機やトラックが入れない狭い場所になると、撤去するための費用が高くなることがあります。
また連結墓地のうちのどちらか一つだけを墓じまいする場合も、掛かる費用は高くなる可能性があるようです。
遺族や親族間のトラブル
墓じまいでは、遺族や親族間でのトラブルも起きる可能性があります。
例えば、お墓を継承する者だけで墓じまいを予定してしまうと、実際に墓じまいを行った後に、残りの遺族や親戚とトラブルになるというケースが実際に起きています。
墓じまいは代行して貰えるの?

墓じまいは遺族や親族が行うのが一般的ですが、中には様々な理由によって行えないケースもあるでしょう。
その場合は、墓じまいの代行業者に依頼することができます。
墓じまいの代行業者は、遺族や親族の意思をしっかりと汲み取って、希望通りにしてくれる墓じまいのプロです。
ただ代行業者によって実際に行って貰える内容が異なりますので、事前に確認をしておきましょう。
例えば、墓じまいの代行業者であるのに行政に関する手続きをしないところもあれば、代行業者に墓じまいを依頼したら内容が予定と違っていたなど、実際にトラブルも起こっているのです。
墓じまいの代行業者には、墓じまいの行政手続きだけを行う弁護士や行政書士などの法律の専門家や、遺骨の取り出しや墓石解体や撤去工事までを代行する石材店などの他にも、墓じまいに関する全ての手続きを代行してくれる業者などもあります。
墓じまいの手続きを専属で行っている行政書士もいますので、希望する方は相談してみると良いでしょう。
墓じまいの方法と手順
墓じまいをは行う際には、以下の手順で行います。
①お墓の中身を確認する
お墓は故人の遺骨を供養していますが、誰の遺骨が供養されているのか、数量や大きさ、破損状態や経過年数、さらに火葬が終わっているかなどを確認しておきましょう。
遺骨の中には骨壺に名前を記載しないケースもありますので、誰の遺骨か分かり次第、印などを付けておくと良いと思います。
②遺骨の移転先を決める
墓じまいを行う際には、遺骨の移転先を決める必要があります。
墓じまいをを行う理由としては「墓守がいない」、「管理費用が掛かる」というケースが多いため、管理や維持費などについても気をつけましょう。
例えば、納骨堂の場合は管理者を選出する必要があり、お墓と同じくらいの維持費が掛かることになります。
③改葬許可申請を行う
遺骨の移動先が分かったら、改葬許可申請を行います。
散骨や自宅供養などを行う際には特に新しいお墓は必要がありませんので、改葬手続申請は不要です。
通常は菩提寺や霊園などに墓じまいのことを伝え、故人の遺骨を引き取ります。
ただお寺によっては手続きが異なることもあり、例えば「最初に改葬届けを提出しないと遺骨は返還できない」というお寺や霊園もあるようです。
そのような場合は、改葬許可申請書にある改葬理由欄には「自宅供養」などと書いて提出すれば良いでしょう。
④お墓を撤去してくれる業者を決める
お墓の解体や撤去は石材店が行うことが多いのですが、自身で決めても構いません。
ただし、あらかじめお寺が指定業者を決めていないか確認しておきましょう。
知らずに他の業者に解体や撤去を依頼してしまうと、後々のトラブルへと発展することがあるからです。
⑤お墓から遺骨を取り出してメンテナンスする
お墓で供養した遺骨は、依頼した石材店のスタッフから取り出して貰います。
お墓に供養していた遺骨は湿気で溶解することやカビが生えることもありますので、そのようなときは新しい骨壺に入れ替える必要があります。
基本的に永代供養を行う場合は、骨壺内の水抜きをして骨壺をきれいな状態にします。
散骨する場合には、乾燥した後に粉骨してから行います。
納骨堂に預ける場合は、洗骨と乾燥や殺菌をして新しい骨壺に入れ替え、自宅供養の場合は水抜きと洗骨や乾燥をして、真空パックに入れ替えます。
このように様々な方法がありますが、分からないことや詳細は葬儀会社のスタッフなどの専門業者に相談してみると良いでしょう。
⑥土葬の際は再火葬を行う
遺骨の中には、火葬をせずに土葬したものも存在します。
その場合は骨壺から遺骨を取り出して、最寄りの役所に申請して再火葬を行いましょう。
⑦墓石を撤去して更地にする
墓石の解体や撤去が終わった後は、その部分の土地を更地にします。
その後は菩提寺などの墓地管理者に永代使用権を返納して、一連の手続きが終了します。
墓じまいでは実際に様々なトラブルが起きていますので、検討する際には十分に注意しておく必要があります。
また墓じまいは代行業者に依頼をすれば代行して貰えますので、自身で行えないと思うときには相談してみると良いでしょう。
墓じまいを行う際には、方法と手順の確認も忘れないように気をつけて行いましょう。
サイトカテゴリー
- お金について
- 貯蓄について
- 仕事とお金について
-
- 『働く』をよく考えるための4つのポイント
- 給与明細の項目をわかりやすく解説!
- 独立したいけど悩んでいる?自営業のメリット・デメリット
- 職種・学歴・男女別お給料事情をチェック!
- 年末調整の流れを4ステップで詳しく解説!
- 『税金』と言うけど、日本にはどんな種類の税金があるの?
- 資格・副業・財形貯蓄で収入は増やせるのか
- 確定申告を理解する為におさえておきたい7つのポイント
- 確定申告で気になる5つのポイント
- 所得税の基本的な仕組みと14種類の所得控除の種類を理解しよう
- 【具体例付】所得税の計算方法を6ステップでわかりやすく解説!
- 収入を増やす方法『資格取得で収入アップ!』
- 雇用保険とは?を理解する為の6つのポイント
- 公共職業訓練を利用するために3つのポイントを把握しておこう!
- 結婚とお金について
- 家と車とお金について
-
- 家を買う時と借りる時にかかる金額をすべて解説します
- 家を購入するタイミングと購入する前の5つのチェック項目
- 住宅ローンを組む前に理解を深める5つのポイント
- マンションと戸建ての特徴と新築と中古のメリット・デメリット
- 住宅購入時に気をつける4つのポイント
- 住宅ローンの返済について知っておかなきゃいけない5つのポイント
- 住宅ローンを借りる時の6つのポイントを理解していないと後々大変なことに…
- 車を購入する前に確認してほしい4つの項目
- 住宅ローンの仕組みを理解していないと思わぬ落とし穴に!?
- 車は都会と田舎、年代や性別によってもその意識が異なります
- 自動車保険の詳細を徹底解説!詳しくなって損しない契約を!
- 保険とお金について
-
- 入院前に知っておきたい5つの予備知識
- 公的保険のすべてを解説します
- 車や住まいの損害保険とそれ以外にもある損害保険について徹底解説!
- 【自動車保険体験談】事故現場は人間性が露呈する
- 保険料を節約するために必要な5つの知識
- 自分に合った保険は年齢や家族の有無によって異なります。年代別に紹介!
- 近年、徐々に注目されている『地震保険』の特徴と補償内容を詳しく解説!
- 加入する前に知っておきたい『こども保険(学資保険)』のメリット、デメリット
- 火災保険が大切だとわかる4つのポイント
- もしものときに備えて、葬儀に係わる最低4つの知識を身に着けよう
- 貯蓄性がある保険についてメリットとデメリットを理解しておこう!
- 生命保険の分類と特徴『定期・終身・養老を比較する!』
- 生命保険には「積立型」と「掛け捨て型」に大きく分ける事ができます
- 社会保険と生命保険の目的
- 国民年金保険料を支払えない時に見てほしい4つの知識
- 会社とお金について
- 老後とお金について
- 葬儀とお金について
-
- 大切な人の危篤を告げられる前に押さえておきたい4つの手順
- 故人の凍結された金融機関の口座から現金を引き出すには…
- 臨終を告げられ病院又は自宅で亡くなった場合の葬儀までの流れ
- 臨終後の連絡をする前に身に着けるべき4つの知識
- 故人が臓器提供・献体を希望していたらどうする?
- 故人が退院するときの4つのポイント
- 『葬祭業者はどうする?』の前に知っておきたい選び方5つのポイント
- 安置と納棺をする時に知っておきたい7つのポイント
- 葬儀社と打ち合わせをする前に身に着けたい7つの知識
- 死亡・火葬・埋葬の書類手続きについて徹底解説!
- 喪主・世話役をきめる為にそれぞれの役割について解説します
- 葬儀の日程と場所を決める為に必要な3つの知識
- 葬儀の形式と今後の葬儀の在り方
- 宗教の概念や思想にとらわれない自由な形式の『無宗教葬』の概要と流れの例
- 近年、葬儀観が変化している。『密葬、家族葬、直葬』とは?
- お別れの会、偲ぶ会の概要・注意点そして具体例を解説
- 戒名の種類とお布施について徹底解説
- 神式・キリスト教式でのお礼
- 昔ながらの習慣『心づけ』の6つのポイント
- 『返礼品・会葬礼状』の準備について4つのポイントをチェックしよう!
- 喪服に関する基本知識・注意点とマナー違反
- 仏式の通夜に関する作法・注意点と具体的な進行例をご紹介
- 神式・キリスト教式の通夜の概要と進行例
- 通夜ぶるまいを行うための5つのポイント
- 【仏式】葬儀・告別式の意味と一般的な葬儀の流れ
- 神式・キリスト教の葬儀の流れ
- お別れの儀・出棺の流れと出棺時のあいさつ例
- 火葬・骨上げの概要と流れ
- 還骨法要と初七日法要の流れと概要
- トラブルを避けるために葬儀費用の一般例と相場を知ろう
- 家族や親類の葬儀が終わった後は近所や親戚などにあいさつ回りを行う
- 葬儀費用の支払いについて紹介
- 忌中と喪中の過ごし方(喪と忌に関する事柄について紹介)
- 香典返しにまつわる疑問を解決
- 遺品整理の注意すべきポイント
- 遺品整理の1つ『形見分け』。気になる点・タブーについて紹介。
- 相手に先立たれた後、親の世話はどうする?
- 本人が死亡した後の名義変更等の手続きについて
- 『葬祭費』『埋葬料』の手続きの方法等について紹介
- 病気で亡くなった場合の高額医療費の申請方法
- 故人が公的年金を受けていた場合の手続はどうすれば?
- 国民年金の加入者がもらえる「遺族基礎年金」について紹介
- 故人が厚生年金に加入していた際の手続きを紹介
- 故人の生命保険を受け取る手続きについて紹介
- 遺族が故人に代わって確定申告を行う際の手続きについて紹介
- お葬式が終わった後の必要書類の取得方法
- お葬式が終わった後の様々な書類を郵送してもらう方法
- 墓地を購入するということについて紹介
- 墓地を購入する方法や手続きでなにが必要なのかを紹介
- お墓を建てる際の注意点
- 近年、新しい埋葬方法が増えてきている
- お墓を別の場所に移す『改葬』。その際の注意点などを紹介
- 位牌を選ぶ際のポイント
- 仏壇を購入する際の注意点
- 毎日の供養は大切。日頃の供養について内容を紹介
- 法要の準備や進め方を紹介
- 法要の案内状やあいさつについて大切な点
- 四十九日などの法要にかかる費用
- お盆やお彼岸は地域によって様々なしきたりがあります
- 配偶者に先立たれ、残された親の気持ちを考える
- 配偶者の死がきっかけでうつ病に…
- 配偶者に死なれた親の気持ちについて、一歩踏み込んだ説明をします
- 親の自立を促す考え方について説明
- 介護が必要になるときに備えどのように準備しておくべきか紹介
- 介護保険についての仕組みやサービスについて紹介
- 認知症がどのようなものかについて説明します
- 高齢者の施設がどのようなものか紹介
- 配偶者に万一のことがあった場合の相続について
- 早急に片付けないといけない法定相続
- 相続の際に重要になってくる遺言
- 法律の定めよりも個人や相続人の考えで相続したいと考える人もいる
- 相続の際に便利に活用できる財産目録
- 相続放棄をどのように行えばいいのかを紹介
- 事実婚の相続について紹介
- 遺言書が見つかったら内容や被相続人の意思の確認が必要
- 遺言の執行について紹介
- 遺言書の内容に納得できない場合の対処方法
- 親に残しておいてもらいたい遺言
- 遺留分や遺留分減殺請求について紹介
- 遺産分割協議をスムーズに進めるために手順や注意点を紹介
- 寄与分があると相続分も変更となるため事前に確認
- 特別受益と寄与分
- 遺産分割協議書は作成する義務はないが、いざというときに役立ちます
- 遺産分割協議が不成立となった場合の手続き
- 遺産ごとの相続手続きのあらまし
- 相続税は手続きが複雑なので早めの準備が大切
- 相続税の対象になる財産
- 相続財産の評価の仕方(不動産)
- 相続財産の評価の仕方(動産)
- 相続税による控除の対象になるものを紹介
- 相続税の計算方法
- 相続税の申告と納税の仕方
- 相続税の申告と納税の仕方を再確認してみることが大切
- 相続税の延納と物納の仕方などを紹介
- 相続や財産管理などの悩みがある時は弁護士に相談する
- 登記手続きの相談は司法書士に
- 公正証書で遺言書を作成する際は公証人に相談
- 相続税の手続きは税理士に相談
- 不動産の調査や測量について土地家屋調査士に相談
- 故人の貯金を相続するときどれくらいの相続税がかかるのか
- 故人の預金口座の名義変更の方法
- 末期の水の紹介
- 末期の水の由来
- 末期の水のタイミングや他の宗教の状況
- 死亡診断書についての取得方法などについてを紹介
- 死亡診断書を発行する手続きなどを紹介
- 様々な場面で死亡診断書が必要になる
- 死亡診断書の写しの扱いなどについて紹介
- 死亡診断書は火葬許可書など、様々な場面で必要になる重要な書類
- 亡くなった家族が携帯電話やスマホを利用していたとき
- 死亡診断書は死亡届の申請など、様々な場面で必要となる書類
- 一般的な生命保険金の請求や、請求権者などについて紹介
- 死亡診断書を葬儀会社に依頼しても問題ない?
- 死亡診断書の提出先や提出期限
- 死亡診断書は犬や猫といった動物の場合は必要となるのか
- 死亡診断書の内容
- 自宅で亡くなった際の手続き
- 死亡診断書の代筆
- 死亡診断書を紛失した場合
- 死亡診断書の発行方法
- 死亡診断書について事前に必要な知識を確認
- 死亡診断書の用途などについて紹介
- 死亡診断書はその用途によって枚数や手続きなどが異なる
- 死化粧についてを紹介
- 死化粧の由来
- 湯灌とはどのようなものかを紹介
- 湯灌を行う時期、作法や立ち会う際のマナー
- 湯灌は専門業者に依頼?
- エンバーミングとは
- エンバーミングの手順
- エンゼルケアとエンバーミングの違い
- 葬儀や火葬を行う前にエンゼルケアに関してチェック
- エンゼルケアの内容や費用
- エンゼルケアで行うクレンジングや、ケアを行うタイミングについて
- エンゼルケアを行う際の準備
- エンゼルケアの目的や由来
- 菩提寺に関すること
- 自分の死後のことを考える際には献体も一つの選択肢
- 葬儀屋の探し方についてのポイント
- 葬儀社の種類
- それぞれのケースに合った葬儀屋を選ぶことが大切
- 葬儀の規模や葬儀屋によって実際にかかる費用
- 葬儀の日付や、葬儀屋の仕事
- 葬儀屋や火葬場についてを紹介
- 納棺式について紹介
- 納棺式の内容を理解しておく必要があります
- 葬儀会社のサービス
- 死亡届の内容
- 死亡届と手続きなどについてを紹介
- 死亡届の記入の仕方や関連事項
- 死亡届の提出期限や、その他の手続きの流れ
- 死亡後に支給されるお金と、死亡届の期限・クレジットカードの解約
- 死亡した後の戸籍
- 被相続人が死亡した場合の手続き
- 死亡届の様々なケース
- 死亡届の使い道など
- 死亡届は土日祝日や夜間でも提出可能
- お葬式の際の喪主の役割
- 喪主や喪主の妻がやるべきこと
- 喪主の役割
- 喪主を頼める人がいない場合にはどうすればいいのでしょうか?
- 一周忌法要の内容
- 世話役とはどのような存在
- 六曜はどのような意味があるのかお葬式との関係
- 大安とお葬式の関係
- 自宅葬の花祭壇やマナー
- 自宅葬の服装や弔問する際のマナー
- 自宅葬の食事や流れ、メリット・デメリット
- 家族葬の祭壇や様々なマナー
- 家族葬にかる時間や会葬礼状
- 家族葬のお通夜や参列者
- ペットと人間の自宅葬や斎場
- 斎場と式場の違いやお葬式の流れ
- 斎場での通夜の晩の宿泊やお寺での葬式費用と葬式マナー
- お寺の葬儀やお布施の相場
- キリスト教式葬儀のマナーや内容
- 自由葬の内容や様々な例
- 自由葬で行われるお通夜の内容や、デメリット
- 自由葬のメリットや費用
- 無宗教の式次第や自由葬の内容
- お葬式の挨拶や位牌、お墓などについて
- 自由葬を選択する際は一般葬で行われる戒名や祭壇、お葬式の内容を確認する
- 自由葬の内容と割合
- 密葬と他の葬儀との違いや弔電について
- 小さいお葬式として人気を呼んでいるのが密葬
- 密葬の香典に関する事柄や、お葬式の費用について
- 密葬は参列しないのが一般的です。その際の案内状は?
- 密葬も一般のお葬式と同じように遺影などが必要になる
- イオンの密葬が参考になる
- 密葬と一般葬との違い
- 密葬の内容について紹介
- 密葬でも会社に連絡は必要?
- 密葬を行う際は事前に内容や手続きなどを把握することが大切
- 密葬の定義や手続きなどを紹介
- 密葬はお寺でも可能
- 一般的なお葬式と密葬の流れに違いはない
- 密葬と他のお葬式との細かい違い
- 密葬後に行われる法要
- 密葬のマナー
- 密葬を行う際のお花や服装などのマナー
- 密葬の割合や詫び状、直葬との違い
- 密葬を行う前に葬儀会社と相談をして疑問点を払拭しましょう
- 密葬の知識を身につけておくことが大切
- 直葬についての内容や納骨、戒名などについてを紹介
- 日本で直葬を実際に行っている人の割合と参列する際の服装やお経
- 直葬に参列する際のマナーを始め、葬儀会社で実施しているプランなどを紹介
- 直葬にかかる費用や参列時の香典、さらには挨拶などのマナー
- 直葬の特徴について紹介
- 直葬を行うときの位牌やお墓、供花についてを紹介
- 直接の忌引きや共同墓地
- 直葬の内容(近所の方への挨拶や供物・献花)
- 直葬を行うときには献体や香典、参列するときの注意点
- 直葬の香典返しの挨拶状など
- 直葬のスケジュールやマナー
- 直葬で準備すべきこと
- 生活保護受給者が葬儀を行う際は直葬?
- 直葬を行う際に注意する点
- 直葬の定義や直葬のトラブル対処
- 直葬と納棺や納骨堂などについてを紹介
- 直葬に反対する家族や親族もいる
- 直葬のメリットや密葬との違い
- 直葬のプランや魅力
- 霊園や遺言、宗派など直葬で気をつける点
- 永代供養とは
- 永代供養の意味や費用などについて
- 永代供養と納骨堂、新盆や挨拶について
- イオンで契約できる永代供養プラン
- 永代供養と遺骨、お盆やお参りについて
- 永代供養料の表書きやお供え、お墓についても検討しておこう
- 永代供養のお墓参りや管理費
- 永代供養の契約を結んだ後の解約や改葬
- 永代供養の契約書や規約
- 永代供養にかかる経費や形態
- もし永代供養先が倒産したら?
- 永代供養付個別墓や香典、散骨について
- 永代供養の法事と続税や税金について
- 永代供養の種類も様々
- 永代供養を申し込みするタイミングや注意事項
- 永代供養の手続きや手順、マナーについて
- 永代供養と埋葬許可書、管理費用について
- 永代供養の手続きと行政書士への相談
- 永代供養墓の合祀やお願いする時期
- 永代供養の実態や相続税、禅宗について
- 永代供養のメリットとデメリット
- 永代供養はどこでできる?
- 犬や猫などペットの遺骨の永代供養
- 菩提寺の永代供養やお墓の費用
- 永代供養には様々なプランがある
- ふるさと納税の返礼品に永代供養墓が?
- 永代供養の歴史や注目される理由
- 永代供養と四十九日法要
- 生前契約で希望するお葬式が実現する
- 生前契約の費用や手順
- お別れの会での平服や弔電文例
- お別れ会のマナー
- お別れの会の流れや日程調整、案内状について
- お別れの会の香典や献花、会費
- お別れの会の案内状の文例や会場選び、行けない時の対応
- お別れの会を欠席する場合のハガキの書き方
- お別れ会での献杯や献花、祭壇
- お別れ会の香典のマナー
- お別れ会の式次第や開催準備
- 社葬やお別れ会の税務処理
- お葬式とは別のお別れ会とはどういうもの?
- お別れの会と偲ぶ会の違いは何?
- 偲ぶ会の開催時期や式次第などについて
- 偲ぶ会の案内文や返信方法
- 偲ぶ会のマナー
- 偲ぶ会での香典マナーと、主催側のお花やお土産について
- お別れの会と混同しがちな『偲ぶ会』についてを紹介
- 偲ぶ会(お別れ会)の案内状やお礼状
- 偲ぶ会に持っていくのは会費か香典か
- 偲ぶ会を運営するのは大変
- 偲ぶ会の開催準備
- 偲ぶ会の服装マナー
- 偲ぶ会の欠席する際の返信メールやはがきの書き方
- お別れの会や偲ぶ会の香典の相場は?
- 偲ぶ会の献杯は乾杯とは異なる
- 偲ぶ会のスケジュールを確認しておくこと
- 偲ぶ会の祭壇や食事、スライドショーについて
- 偲ぶ会での線香やお酒、席次表
- 偲ぶ会での弔辞や弔電
- 偲ぶ会を開くタイミングや案内状について
- 偲ぶ会に遅刻してしまいそうな時はどうすればいい?
- 偲ぶ会を行う時間帯?
- 偲ぶ会の香典マナーや数珠について
- 故人を偲ぶ茶会は可能なの?
- 偲ぶ会は病院で行うこともある
- 戒名やその相場は?
- 浄土宗の戒名の構成について
- 戒名はいらない?戒名がなくても問題ない?
- 戒名の意味・内容を理解しておきましょう
- 戒名の起源や墓石への彫刻、階級について
- 戒名は男性と女性では違う
- 戒名料が高い理由やつけるタイミングとトラブル事例
- 神式の通夜やお盆
- 戒名は日本だけの慣習
- 戒名は自分たちで勝手につけても良いのか?
- 犬や猫のペット葬儀に戒名をつけることはできるの?
- 心付けを渡す際のポチ袋の選び方やお札の入れ方
- 心付けの費用や渡すタイミング
- 会葬礼状と香典返しはどう違うの?
- 会葬礼状の書き方を確認しておきましょう
- 会葬礼状は忌引き申請の添付書類としても利用できる
- 会葬礼状の名前続柄や表書き
- 参列者に渡す会葬御礼と香典返しや処分時期
- 会葬礼状作成時のマナーについて
- 会葬礼状と香典返しは相続税の控除対象になるの?
- 葬儀の会葬礼状はハガキや自作でも大丈夫
- 香典返しと熨斗の書き方
- 香典返しに商品券を贈っても大丈夫なの?
- 香典返しを渡す時期はいつがいい?
- 香典返しをいただいた際のお礼はすべきか
- 喪服のレンタルとマナー
- 男性の喪服マナー
- 女性の喪服マナー
- 赤ちゃんや小学生、中学・高校生の喪服のマナー
- 喪服を着る場所や季節によるマナー
- お通夜と半通夜の違い
- お通夜と告別式の違いや挨拶
- 通夜の受付係のマナー
- 通夜の受付ってだれがやるの?またそのお礼は必要?
- 通夜の参列の流れや参列マナー
- 通夜参列のお礼メールや葬儀用語
- お通夜に遅れるときや告別式の参列をお断りするときのマナー
- お通夜に焼香のみで帰るのは失礼?
- 通夜の参列に必要なものを確認しておきましょう
- 朝に亡くなった場合、通夜はいつ行うの?
- 通夜の延期はできる、できない?
- 通夜振る舞いの意味や挨拶、マナーについて
- 通夜振る舞いは地方によって異なる
- 通夜祭の流れとタイムスケジュール
- 通夜祭の香典や作法・服装について
- 通夜祭の式次第や玉串奉奠
- 直会の意味や挨拶・マナーについて
- 告別式と葬式はどう違うの?
- 弔辞と弔電の違い
- 焼香の意味やマナー
- 出棺の意味や手順
- お別れの儀とはどんなもの?
- 火葬場の挨拶に関する例文
- 火葬場に残った遺骨はどうするの?
- 遺骨の引き取りを拒否できる!?
- 火葬場での火葬の流れ
- 火葬許可証の取得とペットの火葬について
- 火葬場での心づけは必要か?
- 納めの式や火葬中の過ごし方
- 骨上げの流れや骨上げをする人
- 骨上げの方法やマナー
- 火葬許可証の様式や再発行について
- 火葬許可証の保存年限やコピーの使用
- 火葬許可証は土日でも発行は可能か?
- 火葬許可証と埋葬許可証はどう違う
- 火葬許可証の使い道や手続き
- 改葬の手順と費用
- 改葬許可証は改葬の際に必要
- 改葬で必要な事務手続きを確認しておきましょう
- 改葬の際の再火葬の手順はどうなっているの?
- 改葬許可証に有効期限はあるのか
- 墓じまいの手続きや掛かる費用
- 墓じまいのトラブルや手順について
- 墓じまいと永代供養はどのような違いがあるのか
- 墓じまいはいつ行えばいい?
- 墓じまいは誰が行うのか
- 墓じまいのお金がないときはどうすればいい?
- 墓じまいをする際には注意点を確認しましょう
- 魂抜きの方法や必要なもの
- 墓じまいのメリットとデメリット
- 墓じまいを代行するには資格が必要!?
- 魂抜き法要でのお布施袋の書き方や渡し方のマナー
- 手元供養におすすめの骨壷やペットの手元供養
- 仏壇を買った後の開眼供養が必要ですか?
- 開眼供養のマナーについて
- 開眼供養・開眼法要を行うタイミングについて
- 墓石の開眼供養時は石屋さんのご祝儀は必要なの?
- 開眼法要時のお祝いののし袋は、蝶結びと結び切りのどっち?
- 開眼供養の手順や納骨について
- 開眼供養の流れやマナー
- 還骨法要とその流れ、挨拶やマナーについて
- 初七日法要や供え物、挨拶について
- 初七日の開始時間や所要時間
- 初七日のお返しや服装マナー
- 初七日は誰が行けばいいの?
- 初七日の手順やペットの初七日
- 初七日は友引や仏滅にしても大丈夫なの?
- 妊娠中に初七日法要に出席する場合
- 初七日法要は年末年始でもできる?
- 初七日までしてはいけないことってあるの?
- 繰り上げ法要ってどういうもの?
- 繰り上げ法要と四十九日法要
- 繰り上げ法要の香典や香典返し、挨拶について
- 繰り上げ法要で包むお布施の金額は?
- 繰り上げ法要後は何を行うのか?
- 忌明けや忌明けの挨拶状
- 忌中引きと挨拶例文
- 葬儀費用の総額内訳や平均、葬儀費用のトラブル事例
- 葬儀費用はお香典で賄うことはできるのか?
- 葬儀にかかる最低費用や払い戻し
- 葬儀費の遺留分減殺請求と確定申告について
- 葬儀代がない時はどうすればいい?
- 葬儀は種類別によって費用が異なる
- 社葬の費用は経費として計上できる勘定科目もある
- 葬儀費用は地域によって異なる
- 生命保険で葬儀費用をカバーできるのか?
- 葬儀後の挨拶回りや手土産について
- 忌引き、忌中、喪中の違いとは?
- 香典返しや渡すタイミングや熨斗の書き方
- 香典返しの品物に商品券はありなのか?
- 香典返しの意味や会社への香典返し、辞退の仕方
- 香典返しを頂いたらお礼をするべきなのか
- 香典返しの品物は手渡した方がいいのか
- 香典返しをしない場合もある
- 形見分けと遺品整理はどう違う
- 遺品を捨てられない場合はどうすればいい?
- 遺品整理で出てきた指輪やネックレスなどの処分方法
- 遺品整理と遺産整理、遺品と遺留品の違い
- 遺品とお焚き上げによる供養
- 遺品整理をすると運気がアップする!?
- 遺品を勝手に処分するとトラブルになることがある
- 遺品整理で行うお焚き上げや遺品供養とは?
- 遺品整理では相続税に注意する必要がある
- 遺品整理では様々なトラブルが起きている
- 形見分けするものやその時期とは?
- 形見分けに添える手紙やお礼は必要か
- 形見分けの処分や形見分けを含んだ遺言書
- 形見分けは誰が主に進行するのか
- 形見分けには様々なトラブルが起きている
- 家族が亡くなった後の手続き
- 死亡後の手続きは早めに行うこと
- 家族が亡くなった後の手続きを確認しておきましょう
- 死亡後の手続き内容を今一度確認しておきましょう
- 年金・保険請求書の添付書類は?
- 葬祭費や申請方法について
- 葬祭費給付金制度や後期高齢者医療の葬祭費
- 葬儀費用は確定申告で控除してもらえるのか?
- 協会けんぽの埋葬料や埋葬料請求の手続き
- 高額医療費制度と医療費控除はどう違う?
- 後期高齢者医療制度の高額療養費や高額医療費貸付制度の仕組み
- 死亡した場合の年金支払い停止の手続き方法
- 遺族基礎年金はどれくらいの金額になるのか
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給要件や年額の違い
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方もらうには
- 遺族基礎年金と寡婦年金の違いや併給について
- 遺族基礎年金はどれくらいになるのか
- 寡婦年金とはどのような年金なのか
- 寡婦年金の要件や手続き方法を確認しておきましょう
- 寡婦年金はいつからいつまでもらえるのか
- 死亡一時金はいつ頃にどれくらいもらえるのか
- 相続放棄をした場合の死亡一時金
- 遺族厚生年金に税金はかかるのか?
- 遺族厚生年金はいつまで貰えるの?
- 遺族厚生年金の受給者が65歳になったときはどうする
- 遺族厚生年金の長期要件と短期要件とは
- アルバイトをすると遺族基礎年金はどうなるの?
- 遺族厚生年金には所得制限がある
- 遺族厚生年金は相続放棄をしても受給できる
- 生命保険に税金はかかるのか?
- 準確定申告は期限や必要書類に注意
- 準確定申告は不要なケースもある
- 準確定申告でも医療費控除の適用はある
- 準確定申告の期限と罰則、社会保険料控除について
- お墓の購入費用や購入時期を確認しましょう
- 墓地を購入する際にはトラブルに注意
- 墓地の永代使用料には消費税がかかるのか?
- 寺院墓地の檀家制度やトラブル
- 寺院墓地と霊園の違いや寺院墓地の費用とメリット
- お寺の「宗旨宗派不問」には様々な意味合いがある
- 公営墓地・霊園にも樹木葬があるのか?
- 公営の合葬式墓と合葬墓の費用
- 樹木葬は話題のお葬式
- 樹木葬のメリットとデメリット
- 個別で樹木葬はできるのか?
- 樹木葬の手順を知る
- 樹木葬はなぜ人気ががあるのか?
- お墓の購入時期・購入費用・流れについて
- お墓を購入する際の注意点
- お墓を購入する際はトラブルに注意
- 生活保護受給者がお墓を持つ方法
- 寿陵のメリットや注意点
- お墓を建てる前に知っておくべき知識
- 最近では葬儀の形態が大きく変わりつつある